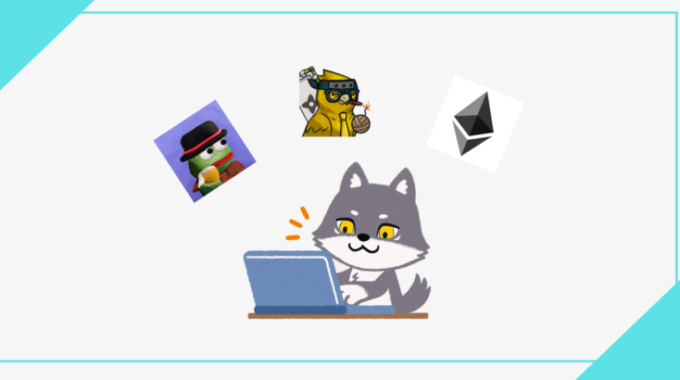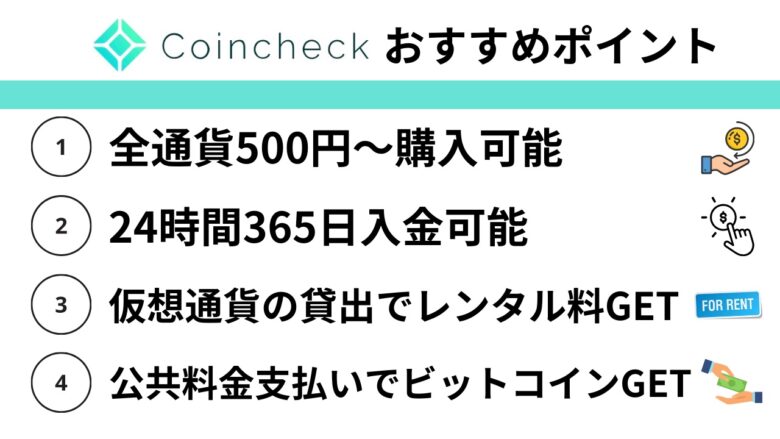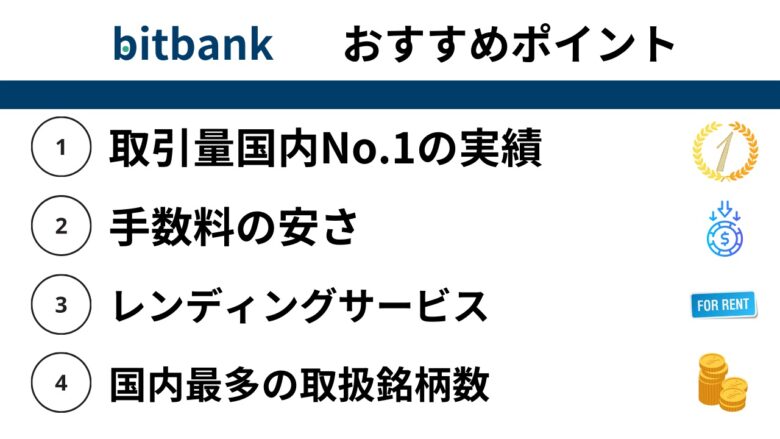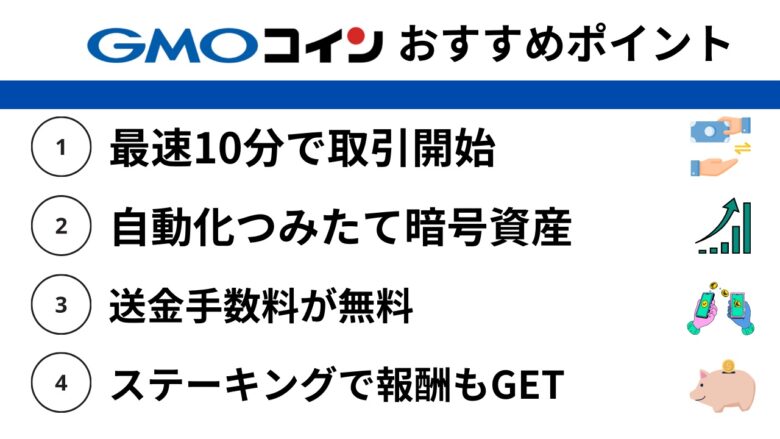Foundationってどんなところ?
OpenSeaと何が違うの?
Foundationのメリットを知りたい
こんな悩みを解決する記事を用意しました。
本記事は海外NFTマーケットプレイス「Foundation」について解説していきます。
700件以上のNFT取引を通じて学んだ経験に加えて、各所のデータを交えて本記事を執筆しています。
FoundationでのNFT販売してみたい方はこちらから本編へどうぞ。

Foundation(ファンデーション)とは
| サイト名 | Foundation |
|---|---|
| 運営開始時期 | 2020年 |
| サイト手数料 | 15% |
| オリジナル作品のNFT化 | 可能 |
| 二次流通 | 可能 |
| 対応通貨 | ETH |
| 対応ウォレット | メタマスク |
| 取扱作品 | デジタルアート |
Foundationは、海外の数あるNFTマーケットプレイス(販売サイト)のひとつ。
取扱いジャンルとしては、NFTアートで決済方法は仮想通貨ETH(イーサ)のみ。
同業他社として、OpenSeaやBlur、X2Y2、Raribleなどが挙げられます。
Foundation2つの特徴
ここでは、Foundationの特徴を解説します。
Foundationの特徴は2点。
それぞれ解説します。
紹介報酬リンクが生成できる
Foundationの特徴として、個別作品の紹介リンクから購入してくれた売上の1%を報酬として受け取れます。
この紹介リンクは同サイトにウォレット接続後作品ページから、無料で誰でも生成可能。
SNS拡散力が強いインフルエンサーに相性がいいツールです。
Foundationならではの機能として、他のプラットフォームにはないものとなっています。
競合他社のOpenSeaとリンクしている
FoundationにNFTを出品すると、OpenSeaも連動して出品登録されます。
逆にOpenSeaにNFTを出品しても、Foundationには出品されません。
売れた場合は、販売に至ったマーケットプレイス側の手数料となり2重に徴収されることはありません。
FoundationにNFTを出品するだけで、OpenSeaとFoundation2箇所で販売可能となるので便利な機能です。
取引所Foundationを使うメリット
Foundationを使うメリットは以下の4つ。
- アートを扱うUIが整っている
- 高品質なNFTアートが取引されやすい
- FoundationでOpenSeaにも自動出品登録できる
- ライバルが少ない
以前はクリエイター招待制による出品とオークション販売に制限していました。
現在ではそれらを廃止し、NFTアート特化のマーケットプレイスに生まれ変わりました。
ここでは、そんなFoundationを使うメリットについてまとめました。
アートを扱うUIが整っている
FoundationはUI(User Interface)が整っていて目にする箇所を惹きつけてくれます。
招待制の廃止以前による高い敷居が、そのまま受け継がれたようなプラットフォームとなっているのが特徴。
最低限の使い勝手は備わっているので、OpenSeaをはじめとしたNFT売買を経験された方であれば戸惑うこともありません。
Foundationは、NFTアートを売買できる環境が整っています。
高品質なNFTアートが取引されやすい
Foundationは、作品魅力が高いNFTアートが多数取引されやすいプラットフォームです。
現在は廃止された招待制により高い敷居を設けていた名残からか、高品質なNFTアート作品が出品されやすい環境が整っています。
サイト全体が、「NFTアート」作品をグッと引き立ててくれる設計なのも魅力を高めてくれています。
Foundationは、NFTアートの販売サイトに特化していることもあり、高品質な作品に多く出会えます。
最も取引されているイーサリアムチェーンで出品できる
Foundationは、NFTの取引で最も使われている仮想通貨ETHのみで売買できるサイトです。
他のマーケットプレイスでは、複数種類の仮想通貨が活用できますが、同サイトはイーサリアムチェーンのみ。
もちろん、イーサリアムはOpenSeaやBlurといった他の取引所でも売買に用いられる仮想通貨です。
ひとつに絞っていることで、どれを使ったらいいのか分からない初心者にも向いています。
FoundationでOpenSeaにも自動出品できる
Foundation NFTを出品すると、自動的にOpenSeaにも登録される機能がついています。
OpenSeaに出品しても通常はOpenSeaのみで売買可能となり、Foundationでは販売されません。
ですがFoundationにNFTを出品するとOpenSeaでも連動して販売開始ができるので販売チャンスも2倍。
OpenSeaでも販売したい場合は販売開始するだけなので、2箇所に出品申請する必要がなく便利な機能です。
ライバルが比較的少ない

OpenSeaやBlurといったマーケットプレイスに比較して、Foundationは利用者が多くありません。
そのためOpenSeaだと出品してもすぐに埋もれてしまう作品でも、発見してくれやすいメリットがあります。
販売に繋がるためには作品を発見してもらわないと始まりませんが、FoundationであればOpenSeaに比較してライバルが少ないのでその分チャンスあり。
Foundationは、ライバルが少ないので埋もれずに目立てるチャンスがあります。
Foundationのデメリット
NFT取引サイトFoundationのデメリットは以下の2点。
以下で解説します。
英語のみに対応している
Foundationのサイトは、すべてが英語表記。
OpenSeaは日本語にも対応していますが、Foundationは英語のみで操作に不安がある方や英語に苦手意識があると操作しづらいかと思います。
翻訳しながら進めることになるため、英語表記でも使えるようになれるまでは不便に感じるでしょう。
手数料が高い
Foundationが設定しているマーケットプレイスの手数料が、他のサイトに比較して高く設定されています。
NFTが売れた際のマーケットプレイスの手数料は
OpenSea:2.5%→期間限定0%
Blur :0.5%
Rarible :1%
X2Y2 :5%
Foundation:一時流通15%、二次流通時5%
と他の主要なプラットフォームと比較しても割高な設定。
高額な手数料を支払ってでもFoundationで販売したい!という何かが欲しいというのが現状です。
FoundationでのNFT販売手順
新規でNFTをFoundationで発行・販売する手順をまとめました。
販売手順は以下の項目。
- NFT化したいアート作品を準備する
- ETH(イーサ)を購入する
- メタマスクを導入する
- メタマスクETH(イーサ)を送金する
- Foundationにメタマスクを接続する
- Foundationで個人プロフィールを作成する
- コレクション作成
- ミント(NFT化)する
- Foundationで販売設定(リスト)する
順番に解説していきます。
FoundationでNFT化する費用はいくら必要?
Foundationでは、新規でデジタルアートをNFT化する際にガス代と呼ばれる手数料が発生します。
ガス代がかかるタイミングは3点。
- コレクション作成時
- NFT化する(ミント)時
- 売りに出す(リスト)時
ガス代は、毎秒価格変動しています。
使用者が多いタイミングだと高騰しますので思った以上に高ければ落ち着くまで避けるのがいいでしょう。
そのほかにも以下のタイミングでガス代は発生します。
- NFT販売価格の値下げ
- NFT出品を中止・取り下げる
このタイミングでもガス代が発生するので、ミスないように進めましょう。
NFT化したいアート作品を準備する
NFTにして出品・販売したいデジタルデータを用意しましょう。

画像をどう用意したらいいの?
ゼロから画像を作る方法は、こちらの記事でまとめていますので参考にしてみてください。
ETH(イーサ)を購入する
続いて、FoundationでNFTを出品する際に必要となる仮想通貨ETH(イーサ)を購入しましょう。

ETHはどこで買えるの?
金融庁の認可を得ている国内仮想通貨取引所であれば基本的にどこで仮想通貨(ETH:イーサ)を購入してもOK。
その中でもおすすめなのがコインチェック・bitbank・GMOコインの3社。
簡単に3社の特徴を解説します。
Coincheck
コインチェックはこんな人におすすめ:暗号資産取引が初めての方
コインチェックは520万DLを突破し、国内暗号資産アプリダウンロード数No1を4年連続で達成した国内屈指の取引所です。
同社が提供している電気/ガスを契約すると、支払い金額に応じてビットコインがもらえるユニークでお得なサービスを展開しています。
またbitFlyerやbitbankで扱っていない、手数料が安いポリゴンチェーンのMATICを直接買える国内でも数少ない取引所です。
国内屈指の会員数をサポートする体制に加えて、誰でも迷うことなく暗号資産を売買できるので、不安な方でも安心して取引できますよ!
\スマホでもサクッとできる!無料開設まで簡単3Step/
bitbank
ビットバンクはこんな人におすすめ:NFTゲームも暗号資産取引もガッツリやってみたい人
ビットバンクは1円未満の単位で暗号資産取引できるのが最大の特徴。
相場の需要と供給バランスが見やすい取引板形式での取引ができるため、暗号資産トレーダーにも好評の取引所です。
スマホアプリでもパソコンでも取引でき、60種に及ぶテクニカル分析ができるため価格変動の激しい暗号資産でもしっかりと分析して臨めます。
日本初のゲーム特化ブロックチェーン「oasys」トークンも、国内取引所ではビットバンクのみ取引できるため、将来的にNFTゲームを視野に入れている方は必須の取引所ですよ!
GMOコイン
GMOコインはこんな人におすすめ:とにかくコストカットしたい人
GMOコインはとにかくコストカットして取引したい人におすすめの取引所です。
なぜならNFT取引だけでなく、暗号資産の銘柄問わず送金手数料が無料だから。
そのため必要な分だけ調達してその都度送金しても、手数料で目減りすることなく丸々支えるめ計算しやすいのがメリットです。
24時間いつでも最速10分で取引開始できる迅速な対応や、500円という少額から定額積立できる手軽さも魅力ですよ!
取引所は口座開設や維持手数料は一切かからないため、複数社使ってみて自分に合う取引所を選ぶのがおすすめです。

実際に私は6社用途に分けて使い分けています
メタマスクを導入する
仮想通貨が購入できたら、仮想通貨とNFTを管理する個人用ウォレットを準備しましょう。
個人用ウォレットはいくつかありますが、最もおすすめなのがMetaMask(メタマスク)。
ユーザー数が圧倒的に多くほとんどの取引で使える汎用性と、Google Chromeの拡張機能で導入できる手軽さが魅力です。
導入にあたっての手順や注意点などはこちらの記事を参考にしてみてください。
メタマスクにETH(イーサ)を送金する
Foundationで必要となる道具を用意しましょう。
必要となるものはメタマスクとETH(イーサ)です。
- 国内取引所でETH(イーサ)を購入する
- メタマスクを導入する
- メタマスク内にETHを送金する
詳細な手順を確認したい方はこちらの記事でまとめていますので参考にしてみてください。
Foundationにメタマスクを接続する
続いて、Foundationにメタマスクを接続しましょう。
メタマスクが会員サイトの登録を兼ねているため、その他面倒なクレジットカード登録や個人情報入力は不要。
手順は
- Foundationにアクセス
- Connectをクリックし、ウォレット選択する
- メタマスクが起動し、署名する
これでFoundationが利用可能になります。
ウォレット接続している間は、設定してあるウォレットアイコンがサイト上に表示されています。
Foundationで個人プロフィールを作成する
ウォレットが接続できたら、Foundationで個人プロフィールを作成しましょう。
同サイト上でNFTを購入するだけなら必要ありませんが、新規で作成・出品する場合にはどんな作成者なのかをアピールできるポイント。
日本語で入力・保存も可能ですが、サイトが英語対応のため翻訳ソフトを活用しながら英語で入力していきましょう。
また、X(旧Twitter)かインスタグラムを連携させないとFoundationでNFT作成・出品できないので合わせて対応しておきましょう。
コレクション作成
Foundation内で自分のコレクションページを作成しましょう。
コレクションページとは、アルバムや表紙のようなもの。
NFT化していくアート作品がコレクションページに収まっていく形になりますので、統一感を持たせるのが重要です。
メタマスクが接続している状態で、Foundationのページ右上にある「Create」をクリックします。
CreateからCollection→Createをクリックしてコレクション作成に入りましょう。
FoundationでNFTをミントする
コレクションページが作成できたら、デジタルアート作品をミント(NFT化)しましょう。
メタマスクが接続された状態で、ページ右上にある「Create」をクリックします。
続いて「NFT」→「Mint」をクリックして作成画面に移動しましょう。
アート作品をFoundationにアップロードして作品名など必要項目を埋めていきます。
Description(ディスクリプション)欄には、各作品のアピールポイントを記入していきます。
これらは後から変更不可のため、間違えたりしないように注意。
記入が終わったら、ガス代を支払ってNFT化しましょう。
Foundationで販売設定(リスト)する
NFT化できたら、商品として販売設定しましょう。
設定を決めるのは以下の2つ。
出品方式は、オークション(Auction)形式か固定価格(Buy Now)の2パターン。
集客できないうちはオークション形式を使わないのが吉。
販売価格を入力すると下に「You’ll receive(あなたの取り分)」が表示されます。
販売手数料を除いて手元に入ってくる割合が表示されるのでうまくコントロールしましょう。
販売価格はいくらが適正?
結論言えば、売れれば正解です。
NFTの価格はいくつか要因が絡み合っています。
そのため、常に「いくら」が適正なのかはわかりません。
似たような作品・コレクションはいくらで販売されているのかも参考にしてみてください。
条件変更するには?
Foundationでは、リスト(売りに出している状態)のNFT販売価格を変更できます。
注意点は2つ。
- 操作には、ガス代と呼ばれる手数料が発生する
- 変更履歴はいつでも誰でもチェックできる
価格変更には、ガス代と呼ばれる手数料が発生します。
このガス代は売り上げから引かれるのではなく、その都度払わないといけないため、出費がかさむのでできる限り避けましょう。
また変更履歴はいつでも誰でもチェックできます。
度重なる変更は購入希望者に不信感を与えてしまいかねませんので、慎重に行うべきでしょう。
Foundationによくある質問
Foundationに対するよくある質問をまとめました。
事前にチェックしておくとトラブル回避できるかもしれませんよ。
Foundationは日本語対応してる?
Foundatioは日本語に対応していません。
翻訳機能(Google翻訳やDeep Lなど)を活用するしかありません。
主な使い方はOpenSeaなどと似ているので、慣れてくるまでは大変かもしれません。
FoundationとOpenSea、どっちがいい?
結論、OpenSeaです。
- 世界最大級の利用者数(販売数・売上数)がいる
- NFT出品手数料がかからない
- 販売手数料がFoundationに比べて安い
Foundationで出すメリットが少ないのが現状です。
Foundationにはアプリはある?
残念ながらありません。
OpenSeaにアプリが導入されていますが、このアプリは閲覧のみで売買できません。
そのためアプリのメリットもほとんどないのが現状。
Foundationは、そもそもアプリはリリースされていません。
FoundationとOpenSeaを連動させるには?
Foundationでリストすると、OpenSeaにも販売前状態の登録まで自動で反映されます。
OpenSea側でも販売する場合、最終的にリストする操作が必要な点に注意してください。
FoundationでNFTが売れた場合
アカウントにメールアドレスを登録しておけば、お知らせ通知メールが届きます。
NFTの場合手数料が引かれた分の売り上げは、NFTと交換で自動的に登録したウォレットに着金します。
Foundationの手数料はいくら?
Foundationは、一次販売時に15%、二次流通時は5%のマーケットプレイス手数料が徴収されます。
そのほかにクリエイターが設定した任意のロイヤリティが二次流通時に差し引かれます。
公式サイトでは、ロイヤリティ10%を推奨しています。
If an NFT you created is listed on another marketplace and sells, that is what is referred to as a "secondary sale".
Foundation pays creators 10% royalties for all secondary sales, when possible.
作成したNFTが他のマーケットプレイスに出品されて売れた場合、それがいわゆる「二次販売」です。
財団は、可能な限り、すべての二次販売について10%のロイヤリティをクリエイターに支払います。
How do royalties work on Foundation?
OpenSeaやBlurよりも現状高い手数料のため、NFT転売で利益確保するのはネックとなりそうです。
OpenSeaで転売された際の売上やロイヤリティは?
結論、一部入らないコントラクトがあります。
EPI-2981というFoundationの共通コントラクトで生成したNFTがOpenSeaで転売された場合は、ロイヤリティが入りません。
OpenSea側でロイヤリティを受け取るためには、OpenSeaの指示に従うようにとあります。
詳しくは公式ページを確認してみてください。
NFTマーケットプレイスFoundationのまとめ
Foundationの現状を振り返りましょう。
- 元は招待制・オークション販売のみに特化していたNFTマーケットプレイス
- 現在は誰でもNFTが出品できる(ただしガス代が発生する)
- 販売方法は固定価格リストとオークション販売が選択できる
- 作品の紹介リンクが生成できる
- OpenSeaと連動して出品できる
- 手数料は高い
招待制をしていた名残がまだ残っている感じはあります。
1つの作品に紹介リンクが生成できる機能は、他のサイトにはみられない特徴です。
他のプラットフォームとの使い分けができるようにしたいですね。